著書
 本書は、シャンソン研究会の設立20周年を機に、研究会のメンバーたちによる論文を学術図書として、科研費の助成を得て刊行したものである。(総頁324頁)
本書は、シャンソン研究会の設立20周年を機に、研究会のメンバーたちによる論文を学術図書として、科研費の助成を得て刊行したものである。(総頁324頁)
出版社のサイト(https://www.osaka-up.or.jp/book.php?isbn=978-4-87259-790-5)。以下、編者の吉田正明氏の「はじめに」の抜粋。
「日本においては、シャンソンの学術研究はいまだ立ち遅れていると言わざるを得ない。宝塚歌劇団のレビューやフランス映画の主題歌や挿入歌、あるいはラジオやレコードなどを通して日本に紹介されて以来、シャンソン・フランセーズは日本独自の音楽ジャンルとして発展し変容をとげたため、本来それが有していた歴史性や多様性を失い、フランスへの憧憬とともに、日本語に翻訳された歌詞(しばしば日本人の感性に合わせて大幅に書き換えられている場合もある)でうたう多くのシャンソン歌手や愛好家を生み出してはきたものの、サブカルチャーとしての側面がより際立つ結果となり、学術研究の対象とはなり得なかったからである。それゆえ20世紀以降のフランスの歌手や歌詞を紹介した書籍や雑誌などは多々見うけられるが、いずれも学術研究の水準に達しているとは言い難い。
このような状況のもと、日本におけるシャンソンの学術研究の基礎を築き発展を目指して2002年に立ち上げられたのが「シャンソン研究会」である。フランスにおけるシャンソン文化の歴史と内実を様々な角度から考察し、フランス文化史のなかに正当に位置づけ、かつ、それがどのような役割を果たしてきたのかを学際的に明らかにするため、これまでフランス文学、フランス語学、西洋史学、美学、音楽学など多彩な分野の研究者や専門家を本研究会に迎え入れてきた。
研究会設立20周年を機に、これまでの会員の優れた論考をまとめ、日本におけるシャンソンの学術研究の発展に寄与するため、日本学術振興会の研究成果公開促進費を獲得して出版されたのが本著である。ここに収められた論考は、19世紀から今日までのシャンソン・フランセーズをめぐる様々な視点からのアプローチであり、いずれも日本においてはほとんど扱われていない先駆的研究の数々である。本書は全部で11章からなっており、一定の形式上の統一を図った上で、文体については論者個々の判断に任せた。それがかえって個性豊かな論考となり、多彩なテーマとともに単調さを防ぎ読む楽しみを増しているとも言えよう。本書を通して読者諸氏が、民衆文化の花束たるシャンソン・フランセーズの魅力とその実相の一端に触れられんことを切に願うものである。」
【目次】
【担当部分】
村田京子「19世紀フランスの歌姫ポリーヌ・ヴィアルド」(pp.29-57)
本稿では、日本ではほとんど知られていないが、19世紀のヨーロッパにおいてその名を轟かし、20世紀のマリア・カラスのような存在であったオペラ歌手ポリーヌ・ヴィアルドの生涯を紹介した。当時のオペラ事情だけでなく、歴史的事件や音楽家(リスト、ショパン、マイヤベーア、ベルリオーズなど)や作家(ジョルジュ・サンド、ツルゲーネフなど)との交友関係にも着目し、当時のジェンダー観も考慮にいれながら、彼女が果たしたブルジョワ的オペラと庶民的なシャンソンとの橋渡し的役割を考察した。
【関連リンク】「花だより」58号(発行:中村啓佑編集長):本の紹介
総頁数352頁+別丁カラー図版16頁(出版社サイト:http://www.suiseisha.net/blog/?p=18887)
【概略】作家たちは服装の記号を駆使していかに作品を描いたのか?
前著『イメージで読み解くフランス文学』では、19世紀フランス文学を作品と密接に関連する絵画・彫像と結びつけながら、ジェンダーの視点で考察した。とりわけゾラの『ナナ』や『獲物の分け前』では、女主人公の着る服装は社会的記号となっていた。本書は、その続編として、絵画など美術作品とも連関させながら、モードの観点から文学作品を読み解く試みとなっている。
19世紀は、モード史の観点から見て、服装に大きな変化をもたらした時代であった。フランス革命前のアンシャン・レジーム下では、服装はその形状・質・色が身分別に法律で定められ、とりわけシルクやレース、貴金属など贅沢な装飾品は特権階級のみに許されていた。革命後は「服装の自由」が政令によって明文化され、理論的には誰でも自由に服装を選べるようになった。したがって、服装にこだわりを持つダンディたちを顧客とする高級仕立屋が現れ、女性服に関しても19世紀後半にはオートクチュールの祖、ウォルトが登場する。衣料品店の形態に関しても、従来の薄暗い店舗から明るく大きなショーウィンドーを持ち、色とりどりの布地が美しく並べられた「マガザン・ド・ヌヴォテ」が出現し、さらに第二帝政期にはデパートが誕生する。こうした変化を忠実に反映したのが、同時代の文学先品である。したがって、本書では、19世紀フランス文学を服装やモードを通して、社会的・歴史的・文化的観点およびジェンダーの視点から読み解いた。
第一章では、フランス革命末期の反革命運動を扱ったバルザックの『ふくろう党』を取り上げ、服装と革命の関わりを明らかにしている。第二章では、ジョルジュ・サンドの『アンディヤナ』において、女主人公の服装や変装に焦点を当て、女性作家の視点に立った服装描写の分析を行った。第三章では、バルザックの『幻滅』において、地方とパリの風俗の違いを、服装を通して検証すると同時に、バルザックのダンディズムについて考察した。第四章では、バルザックの『骨董室』と『カディニャン公妃の秘密』に登場する「モードの女王」が、服装の記号を駆使し、どのような女性を演じたのかを検証した。第五章では、エドモン・ド・ゴンクールの『シェリ』を取り上げ、第二帝政期の上流社会(オートクチュールの世界)に生きる女主人公の少女時代から19歳の若さで死ぬまでの成長過程を、服装を通して辿った。第六章では、ゾラの『ボヌール・デ・ダム百貨店』において、デパートがいかに女性の欲望を煽り、買い物熱を掻き立ていくか、その基盤となる「女性の搾取」に焦点を当てて分析した。
以上のような考察によって、時代とともに移り変わるモードを19世紀の作家がどのように捉えていたか、多少なりとも把握できたように思う。さらに、第二章では「ズボンを巡る争い」に触れたが、フランスにおいて女性がズボンを穿く権利を正式に獲得するには、長い年月が必要であった。女性にズボンを穿くことを禁じた1800年の警察条例が廃止されたのは、つい最近(2013年)のことである。このように、服装の問題は19世紀に留まらず、現代にも深く関わるテーマで、本書がこうした問題を考えるきっかけとなれば、幸いである。
【本書に関する書評】
cahier34(日本フランス語フランス文学会、高岡尚子氏、2024年9月、pp.21-23)
 本書は、2021年9月24日、25日に日仏会館主催で行われたシンポジウム「文学作品に現れたフランス革命」(リモート開催)での7名の報告と討論をもとにした論集となっている(総頁244頁)。なお、白水社の雑誌「ふらんす」web版には、執筆者のうちの3人(三浦氏、西永氏、小野氏)の座談会が掲載されている(白水社のサイト参照)。以下、編著者の三浦信孝氏の「緒言」の抜粋。
本書は、2021年9月24日、25日に日仏会館主催で行われたシンポジウム「文学作品に現れたフランス革命」(リモート開催)での7名の報告と討論をもとにした論集となっている(総頁244頁)。なお、白水社の雑誌「ふらんす」web版には、執筆者のうちの3人(三浦氏、西永氏、小野氏)の座談会が掲載されている(白水社のサイト参照)。以下、編著者の三浦信孝氏の「緒言」の抜粋。
「本書では、1789年7月14日のバスティーユ襲撃に始まるフランス革命の時期を実際に生きたスタール夫人とシャトーブリアン、1799年、革命のサイクルに終止符を打った「ブリュメール18日」のクーデタの直後に生まれ、ナポレオン帝政期(1804-14)と復古王政期(1815-30)に人となったバルザックとヴィクトール・ユゴー、そして1844年にフランス革命資料を専門とする古書店の息子として生まれ、ドレフュス事件と第一次大戦のあいだの1912年に「恐怖政治」を扱った小説を出版したアナトール・フランス、フランスより一回り下の世代だが、ドレフュス事件から両大戦間の人民戦線期にかけて『7月14日』から『ロベスピエール』まで「革命劇」連作8篇を書いたロマン・ロラン、そして私たちと同時代の作家シャンタル・トマが、マリー=アントワネットを主人公にバスティーユ陥落から三日間のヴェルサイユ最後の日々を回想した小説を取り上げる。
フランス革命は「自由・平等・友愛」を標語にするフランス共和国の出発点であり、革命をどう記述するかはフランスのナショナル・アイデンティティ構築の鍵を握るだけに、ジュール・ミシュレによる『フランス革命史』(1847-53)から今日に至るまで、歴史家による革命史は枚挙にいとまがない。[…]20世紀に入り、歴史資料にもとづく実証的な革命史研究が進むにつれ、科学としての歴史とフィクションとしての歴史小説は分離する傾向にあり、現代においてはユゴーの『93年』やアナトール・フランスの『神々は渇く』に匹敵する歴史小説は書きにくくなっている。[…]
しかし、ユゴーの『レ・ミゼラブル』がミュージカルになっても映画化されても、原作は圧倒的生命力を失っていない。活字文化にこだわる私たちは、革命史の専門家ではないが、フランス革命を主題として取り上げた7人の作家の文芸作品を通して、それぞれの世代にとってのフランス革命、ひいては現代の人間社会にとってのフランス革命を考える機会にしたいと思い、本書を編んだ。」
【担当部分】
村田京子「第1章 スタール夫人はなぜ、ナポレオンの怒りを買ったのか――スタール夫人『デルフィーヌ』『コリンヌ』」(pp.13-43)
 スタール夫人は、18世紀のアンシャン・レジーム期のフランスに生まれ、ルイ16世の財務総監ネッケルの娘として政治の最前線でフランス革命を体験し、革命末期に台頭してきたナポレオン・ボナパルトと対立して国外追放されるなど、激動の時代を生きた作家である。彼女は1793年にマリー=アントワネットを擁護する『王妃裁判についての省察』を出版して以来、政治に関する様々な論考を発表し、革命後も『フランス革命の主要事件に関する考察』を執筆するなど、政治的発信を行ってきた。小説に関しても、彼女の代表作『コリンヌ』は、ナポレオンによって国外追放されていた時期に執筆された作品で、彼女が国外追放の憂き目にあったのも、まさに前作『デルフィーヌ』がナポレオンの怒りを買ったためである。したがって、本章では『デルフィーヌ』『コリンヌ』を通して、スタール夫人における革命観を検証すると同時に、これらの著作によって、彼女がなぜナポレオンの怒りを買ったのか、その理由を考察した。
スタール夫人は、18世紀のアンシャン・レジーム期のフランスに生まれ、ルイ16世の財務総監ネッケルの娘として政治の最前線でフランス革命を体験し、革命末期に台頭してきたナポレオン・ボナパルトと対立して国外追放されるなど、激動の時代を生きた作家である。彼女は1793年にマリー=アントワネットを擁護する『王妃裁判についての省察』を出版して以来、政治に関する様々な論考を発表し、革命後も『フランス革命の主要事件に関する考察』を執筆するなど、政治的発信を行ってきた。小説に関しても、彼女の代表作『コリンヌ』は、ナポレオンによって国外追放されていた時期に執筆された作品で、彼女が国外追放の憂き目にあったのも、まさに前作『デルフィーヌ』がナポレオンの怒りを買ったためである。したがって、本章では『デルフィーヌ』『コリンヌ』を通して、スタール夫人における革命観を検証すると同時に、これらの著作によって、彼女がなぜナポレオンの怒りを買ったのか、その理由を考察した。
【本書に関する書評】
『日本経済新聞』(2022年9月10日、小倉孝誠氏)
 本書は、2017年6月19日~22日にフランスで開催されたジョルジュ・サンド国際シンポジウムGeorge Sand et le monde d’objets(「ジョルジュ・サンドとモノの世界」)〔6月19日、20日は、クレルモン=フェラン=オーベルニュ大学、6月21日、22日はサンドの故郷ノアンの館が会場〕で研究発表したものの一部を論文集としてまとめたものである。本書では、サンドの小説の中に登場するモノや、ノアンの館のサンドとゆかりのあるモノなど、モノを中心とする様々な分析が展開されている(村田はサンドの『ジャンヌ』において、女主人公が彫像=美術品に喩えられているその象徴的意味を探った)。総頁数510頁。【出版社へのリンク】
本書は、2017年6月19日~22日にフランスで開催されたジョルジュ・サンド国際シンポジウムGeorge Sand et le monde d’objets(「ジョルジュ・サンドとモノの世界」)〔6月19日、20日は、クレルモン=フェラン=オーベルニュ大学、6月21日、22日はサンドの故郷ノアンの館が会場〕で研究発表したものの一部を論文集としてまとめたものである。本書では、サンドの小説の中に登場するモノや、ノアンの館のサンドとゆかりのあるモノなど、モノを中心とする様々な分析が展開されている(村田はサンドの『ジャンヌ』において、女主人公が彫像=美術品に喩えられているその象徴的意味を探った)。総頁数510頁。【出版社へのリンク】
【目次】(table des matières)
Présentation de l’éditeur
George Sand n’est ni sociologue ni peintre d’objets, et pourtant ces derniers ont beaucoup compté dans sa vie domestique et créatrice et, dès leur perception première, dans sa vision du monde. Ce livre montre la place qui fut la leur dans son quotidien et dans sa relation à l’écriture.
【担当部分】 Kyoko Murata : « Signification de la statue dans Jeanne » (pp. 311-326)
【要旨】(Résumé)
Dans le Prologue de Jeanne, trois jeunes hommes mettent chacun une pièce de monnaie dans une main d’une belle fille endormie qu’est Jeanne. Ces trois pièces ne sont pas simplement des choses, mais joueront un rôle symbolique, agissant sur leurs destinées aussi bien que sur celle de Jeanne. De plus, il y a un autre objet qui s’impose dans ce roman : une statue. Dans le Prologue, Jeanne est comparée à une statue antique. Comparer la beauté parfaite à une statue grecque, c’est un cliché qu’on utilise souvent dans les romans. Certes, mais Jeanne est surprise en plein sommeil et exposée sans défense au regard des trois hommes. Sa pose gracieuse avec son bras rejeté au-dessus de sa tête rappelle une statue de Vénus. Cette pose, communément associée au nu féminin, signifie un corps offert aux spectateurs. Cela nous permet de dire que ces hommes regardent Jeanne comme un objet d’art. Tout le long du roman, elle est comparée à de nombreuses statues telles que la Madeleine de Canova et la Galatée. Pourquoi Jeanne est-elle traitée si fréquemment comme une statue ? Nous nous proposons donc de vérifier la signification symbolique d’une statue dans ce roman, en tenant compte de celle des trois pièces de monnaie.
D’abord, nous allons traiter la scène où l’attitude de Jeanne, plongée dans la douleur, rappelle à Guillaume la Madeleine de Canova. Nous allons examiner pourquoi Sand a recours à cette statue, quelle est la différence entre les points de vue féminin (sandien) et masculin (balzacien) sur cette statue, et quel impact a cette image de Jeanne sur le Guillaume romanesque. Et puis, au travers de la Galatée, l’image que se fait de Jeanne Marsillat, avocat libéral et voltairien, nous allons voir la réification d’un corps féminin. Enfin, nous allons examiner comment Jeanne réagit contre les regards masculins et ce que signifie l’image de la statue pour elle-même.
【本書に関する書評】
Cahiers George Sand, No 44, 2022 (pp. 240-244 ; François Kerlouégan)
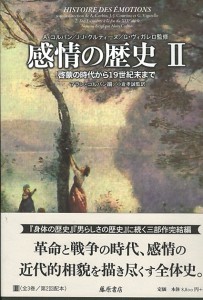 本書は、アラン・コルバン、ジャン=ジャック・クルティーヌ、ジョルジュ・ヴィガレロ監修による『感情の歴史』(Histoire des émotions) 全3巻の、第Ⅰ巻『古代から啓蒙の時代まで』に続く第Ⅱ巻『啓蒙の時代から19世紀末まで』〔アラン・コルバン編、小倉孝誠監訳、総頁数669p.〕の翻訳書である(第Ⅲ巻は『19世紀末から現代まで』)。さらに、『感情の歴史』は、既に翻訳書が出ている『身体の歴史』『男らしさの歴史』に続く三部作の完結編ともなっている。本書は8人で翻訳を担当し、村田もその一員である。
本書は、アラン・コルバン、ジャン=ジャック・クルティーヌ、ジョルジュ・ヴィガレロ監修による『感情の歴史』(Histoire des émotions) 全3巻の、第Ⅰ巻『古代から啓蒙の時代まで』に続く第Ⅱ巻『啓蒙の時代から19世紀末まで』〔アラン・コルバン編、小倉孝誠監訳、総頁数669p.〕の翻訳書である(第Ⅲ巻は『19世紀末から現代まで』)。さらに、『感情の歴史』は、既に翻訳書が出ている『身体の歴史』『男らしさの歴史』に続く三部作の完結編ともなっている。本書は8人で翻訳を担当し、村田もその一員である。
「感情」は時代や文化、個人によってその現れ方が違う。本書の「総序」の一部を引用してみよう。「恐怖、恥辱、怒り、喜びはおそらくいつの時代にも観察されるし、一つの時代から別の時代になっても理解され、「把握される」ように思われるが、じつは個人によって、文化によって、感受性によって異なるのだ。これらの感情には独自の状態と変遷があり、変化し、個別化し、一般的に広く存在するとはいえ細分化された可能性を示す。」こうした「感情の歴史」を時系列的に様々な観点から探ったのが本書で、とりわけ19世紀は「感情の歴史」においてきわめて豊かな時代であった。すなわち、「繊細な魂の覚醒とそれに由来するものが、人々の感動のしかたや特異な感情のゆるやかな刷新によってきわめて特殊な時代を描きだす。こうして個人の内面であれ、自然と他者と社会を感じる新たな方法が生まれる」(「序文」より)時代であった。
本書は16章に分かれ、各専門分野の研究者による論文集となっている。その特徴は次のようなものだ。「内面性、私生活、気候、風景、革命、政治運動、戦争、死刑、宗教、芸術などは、いずれも文化史、社会史、政治史、制度史、宗教史、文化史、美術史の分野で研究され、見事な成果をあげてきた。それを個人と共同体の感情という視座から分析した本書の各章は、人間の歴史の新たな側面を浮き彫りにしてくれたのである。感情は個人レベルにとどまるものではなく、集団的な次元を有する。その境界線はしばしば微妙だが、感情の集団的次元に絶えず配慮しているのが本書の価値の一つであろう」(「監訳者解説」より)。さらにその分析の手段として自伝や回想録、手記、日記、書簡など「個人の内面性とプライバシーを伝える言説」(同上)を積極的に活用し、警察や司法関連資料など公的資料には見いだせない文学的要素と深く関わっていることも本書の特徴である。
【翻訳担当部分】
・アニェス・ヴァルシュ「第9章:感じやすい魂から感情の科学的出現へ――私的領域における感情の濃密化」(pp.309-340)
・ギヨーム・キュシェ「第14章:宗教的感情の刷新」(pp.471-511)
総頁数288頁(出版社サイト:http://www.suiseisha.net/blog/?p=11219)
【概略】(白黒図版の他にカラー図版も多数掲載)
〈女/男らしさ〉とは何か?
文学作品は、時代を超越した普遍的な価値観を担うと同時に、作品が生み出された社会におけるジェンダー観を色濃く反映している。とりわけ、「近代小説の祖」とみなされるバルザックが登場してからは、なおさらである。文学史においてバルザックは「レアリスムの祖」と目されているように、現実をありのままに描いた彼の作品は、19世紀当時の社会の風習、思想、ジェンダー観を忠実に反映していると考えられる。それはバルザックに留まらず、19世紀の多くの作家に当てはまる。したがって、本書では「近代小説」をジェンダーの視点から分析していきたい。また、芸術小説、芸術家小説を多く生み出したのも、19世紀の作家たちである。ルーヴル美術館の一般開放や、サロン(官展)への一般参加が認められるようになるのは、フランス革命後であり、革命後に経済的覇権を確立したプチブルジョワたちが文化的教養を求めてサロンに殺到するようになる。また、複製画やリトグラフ(石版画)の普及によって、小説の読者である一般大衆にとって、絵画が身近なものとなった。
それゆえ、本書では19世紀フランス文学を、作品と関連のある絵画や彫像などのイメージを媒介にして、ジェンダーの視点で読み解いていく。さらに本書の特徴は、19世紀に覇権を握ったブルジョワ階級の父権的な価値観に基づく「女らしさ」「男らしさ」の範疇から外れる人物に焦点を絞って、作品を分析していることにある。こうした人物がどのような点で「女らしさ」「男らしさ」に欠けるのかを検証することで、当時のジェンダー観をより一層、浮き彫りにすることができよう。
第一章では、スタール夫人の『コリンヌ』を取り上げ、男の領域とされる「公的空間」で華々しく天分を発揮した女性詩人が、いかに悲劇的な末路を遂げるのか、その過程を絵画・彫像などのイメージを通して探っていく。第二章では、男を破滅させる「宿命の女」像を、「宿命の女」を描いた絵画を参照しながら、19世紀前半のバルザックの作品において検証する。第三章では、ゾラの『ナナ』を取り上げ、19世紀後半の第二帝政期における危険な娼婦像を、印象派のマネの絵画などと関連づけて分析する。第四章では、同じくゾラの『獲物の分け前』を取り上げ、娼婦のナナと対極をなす社交界の女王、ルネの身体がいかに男たちに搾取されていくのか、当時のモード、ファッション・プレートや絵画を通じて見ていく。第五章では、第四章までとは逆に、「男らしさ」の範疇に当てはまらない、両性具有的な男性を取り上げる。そして、彼らがどのように描かれ、どのように「男らしさの危機」と関連しているのか、ロマン主義文学から自然主義文学にかけて探っていく。
こうした分析作業を通じて、19世紀フランスに限らず、現代の日本にも通じる「女らしさ」「男らしさ」の観念への問題提起を行っていきたい。また、絵画・彫像などイメージを介することで、文学作品の読解に新たな視野が広がることを期待している。
【本書に関する紹介記事・書評】
「花だより」15号(2019年11月25日:中村啓佑氏、p.5)
『女性空間』37号(日仏女性研究学会、2020年12月:岡部杏子氏、 pp.125-126)
cahier 27(日本フランス語フランス文学会、2021年3月:高岡尚子氏、pp.24-26)
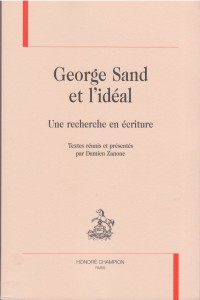 本書は2013年6月20~22日にベルギーのLouvain-la-Neuveカトリック大学で開催されたジョルジュ・サンド国際シンポジウムで研究発表をしたものの一部を論文集として本にまとめたものである。サンドはバルザックを始めとするレアリストに対して理想主義者(idéaliste)として、世界のあるべき理想像を描いた作家とみなされている。本書は、サンドの小説や戯曲、自伝などを通して窺えるサンドの「理想」(理想の詩学、理想の芸術家像など)を様々な観点から探っている(村田は「理想の女性画家像」について論じている)。総頁数465p。(出版社へのリンク)
本書は2013年6月20~22日にベルギーのLouvain-la-Neuveカトリック大学で開催されたジョルジュ・サンド国際シンポジウムで研究発表をしたものの一部を論文集として本にまとめたものである。サンドはバルザックを始めとするレアリストに対して理想主義者(idéaliste)として、世界のあるべき理想像を描いた作家とみなされている。本書は、サンドの小説や戯曲、自伝などを通して窺えるサンドの「理想」(理想の詩学、理想の芸術家像など)を様々な観点から探っている(村田は「理想の女性画家像」について論じている)。総頁数465p。(出版社へのリンク)
Présentation de l’éditeur
« J’ai besoin d’idéal » : cette confidence de George Sand peut servir de fil conducteur pour lire l’ensemble de son œuvre et en saisir l’unité comme recherche continue. Poétique, esthétique, morale, politique, religion : tous ces domaines sont autant d’occasions de formuler l’exigence d’idéal. La notion est obsédante, inquiétante, salvatrice. Quel peut être l’idéal ? Comment l’atteindre et comment le reconnaître si jamais il est là ? Toute page écrite par Sand peut être lue comme une étape de recherche dans l’éblouissement de ce grand mirage.
【担当部分】Kyoko Murata : « La figure idéal de la femme peintre dans l’œuvre de George Sand » (pp.379-388)
On peut trouver plusieurs œuvres de Sand, traitant de sujets artistiques. Sur la musique, on peut citer à titre d’exemple Consuelo, La Comtesse de Rudolstadt, et Les Maîtres sonneurs, et puis sur le théâtre, Lucrezia Floriani et Le Château des Désertes, enfin sur la peinture, Les Maîtres mosaïstes. Mais il y a une grande différence entre les romans de la musique et du théâtre, et ceux de la peinture : l’auteur dépeint Consuelo comme la figure idéale de musicien, ou traite de théâtre idéal dans Le Château des Désertes, alors que dans les romans où apparaissent les personnages-peintres, Sand ne nous montre pas nettement la figure idéale de peintre. Dans Les Maîtres mosaïstes, il s’agit d’une hiérarchie entre l’artisan (le mosaïste) et l’artiste (le peintre), et l’auteur fait ressortir plutôt le monde du premier. Quant au Paul d’Horace, malgré son talent, il renonce à devenir peintre pour nourrir ses sœurs et sa bien aimée. Cependant il existe une œuvre qui raconte le processus de croissance d’une enfant, celle qui deviendra une véritable peintre professionnelle : Le Château de Pictordu.
Bien que Le Château de Pictordu soit un conte merveilleux pour les enfants, on peut le considérer aussi comme un roman de la peinture. Ce qui est à remarquer chez Sand, c’est qu’il s’agit d’une femme peintre, et non pas d’un peintre masculin. Dans le mythe romantique de Pygmalion, la création artistique est réservée aux artistes masculins, ainsi dans l’œuvre balzacienne par exemple, les femmes ne jouent que le rôle de modèle ou celui de muse. Nous nous proposons donc d’analyser comment George Sand dépeint une femme peintre professionnelle et comment celle-ci atteint le « beau idéal », pour cerner la figure idéale de la femme peintre chez Sand. Pour ce, en dehors du Château de Pictordu, nous examinons aussi Elle et Lui, ouvrage qui est regardé en général comme un roman à clefs, concernant l’amour de Sand et de Musset, mais dont l’héroïne est peintre de portrait.
総頁数 217 頁
【概略】
フランス文学と芸術の関わりは深く、画家、音楽家、彫刻家を主人公とする芸術家小説をはじめとして、音楽や美術に関連する作品が多く見出せる。本書は、絵画がフランス・ロマン主義文学の中でどのように扱われているのかを探るものである。例えば「近代小説の祖」と呼ばれるバルザックは、女性を描写する際に、ラファエロの聖母像など絵画を引きあいに出すことがしばしばであった。しかし、人物描写において絵画を参照するようになるのは、実はバルザックの生きた時代、すなわち19世紀前半からに過ぎない。その理由として、①フランス革命後のルーヴル美術館の一般開放、②複製画やリトグラフ(石版画)の普及、③経済的に余裕のできたプチ・ブルジョワが文化的教養を求めたことの3点を挙げることができる。小説の読者である大衆にとって、絵画はより一層身近な存在となったわけだ。その結果、読者に登場人物のイメージを喚起させるために、絵画を比喩として使うことが可能になった。例えば小説の中で、「彼女はモナリザのような神秘的な微笑を口に浮かべていた」と表現するには、一般的な読者がレオナルド・ダ・ヴィンチの絵を知っていることが前提となる。
文学作品で絵画が言及される場合、それがどのようなメタファーとして使われているのか、見定める必要がある。そこには芸術的要素だけではなく社会的要素、とりわけ人物像には「男らしさ」「女らしさ」に関する当時の社会的通念が無意識のうちに投影されている。それゆえ、こうしたジェンダーの観点から、バルザックやテオフィル・ゴーチエ、マルスリーヌ・デボルド=ヴァルモール、ジョルジュ・サンドらロマン主義作家の作品を取り上げ、絵画受容の相違点―とりわけ男性作家と女性作家の視点の違い―を浮き彫りにする。以上のように、本書では文学作品と絵画との相関性を探ることで、文学作品の新たな読解を試みていきたい。
【本書に関する書評・紹介記事】
『ふみのさと便り』21号(2015年3月21日:中村啓佑氏)
『ふらんす』(白水社)(2015年8月号:小倉孝誠氏)
日本フランス語フランス文学会cahier17(2016年3月:坂本千代氏、pp.33-34)
本書は編集者の言葉を借りれば、「西洋美術史研究を中心として、ある時代の都市のアート・シーンについて考察しようとする学術論文集のシリーズ」で、「芸術生産の場としての都市」という観点から、19世紀のパリを取り上げたものである。また、本書は「都市という限定された空間を、芸術生産の原動力となる環境として積極的に捉え直し、従来の都市と美術のあり方を内側から書きかえること」を目指し、3つの視点―「越境性と社会的文脈」、「芸術家を含めた人やもの、情報の『混交』」、「アイデンティティ」―を意識し、美術史だけではなく、音楽、建築、文学、哲学など他の学問領域の専門家の論考も含んでいる。学問領域横断という本書の目的に基づき、美術史の専門家ではない村田も寄稿している次第である。様々な領域の専門家による学術論文集に今回初めて参加したが、それぞれが刺激的で示唆に富む論考で、今後の研究に大いに参考にさせて頂くつもりである。19世紀フランスは、テオフィル・ゴーティエやボードレール、ユイスマンス、ゴンクール兄弟のように、美術評を書く小説家・詩人や、フロマンタンにように絵を描く小説家を輩出している。演劇、バレエも盛んで、まさに様々な芸術・文化の混交が特徴で、パリはその中心であった。その点でも多角的な視野のもとにまとめられた本書はユニークなものであると言えよう。
【担当部分】
・村田京子:「ロマン主義的クルティザンヌからゾラのナナへ―19世紀フランス文学における娼婦像の変遷―」(pp.129-148)
自然主義作家エミール・ゾラの『ナナ』は、19世紀後半の第二帝政期フランスにおける娼婦像を描いた小説である。ゾラはこの小説において、ロマン主義時代に席巻した「恋するクルティザンヌ」の脱神話化を目指し、「真の娼婦」を描こうとした。本稿では、ロマン主義的クルティザンヌと一線を画すゾラの娼婦像を見極めるために、ロマン主義文学からゾラの『ナナ』に至る娼婦像の変遷を、それぞれの女性像に関わる絵画的表象と結びつけながら考察した。取り上げる作品はアベ・プレヴォーの『マノン・レスコー』、デュマ=フィスの『椿姫』、バルザックの『従妹ベット』などで、そこに描かれる娼婦像とゾラのナナとの根本的な違いを社会的背景を考慮に入れながら、明らかにしている。ゾラのナナについては、印象派のマネやルノワールなどの絵画との関連を探っている。
Palacios, Concepción / Méndez, Pedro (éds.), Peter Lang (Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien), 366 p.
Espacios Literarios en Contacto. Tomo 4, Collección dirgida por Àngels Santa
本書はスペインの研究者グループを中心とする19世紀フランス中篇・短篇女性作家に関する研究論文集で、男性作家が大多数を占める19世紀フランスの文壇で、ともすれば歴史に埋もれがちな女性作家たちがエクリチュールを通してどのように自らの声を聞かせようとしたのかを探るものである。総勢22名の研究者による論文集で、スタール夫人やジョルジュ・サンド、マルスリーヌ・デボルド=ヴァルモール、ルイーズ・コレのような比較的知名度の高い女性作家の他にも、ダブランテス伯爵夫人、アンナ・ド・ノアイユ、ラシルド(村田は女性ジャーナリストの草分け、デルフィーヌ・ド・ジラルダンを取り上げた)などを扱っている。
【目次】(Table des matières)
Présentation de l’éditeur
Cet ouvrage collectif est une continuation d’une série d’études autour de la nouvelle en langue française publiées grâce à deux projets de recherche (Ministère de Science et Innovation Espagnol et Fondation «Séneca» de la Région de Murcia). L’approche des femmes qui ont écrit des nouvelles étant un aspect peu exploré et qui peut conduire à des découvertes intéressantes, les auteurs proposent cette fois-ci une monographie liée à l’idée de genre, avec l’objectif d’entreprendre de nouvelles pistes de recherche autour du récit court français. Les noms féminins n’abondent pas parmi les auteurs de nouvelles au XIXe siècle et leur production ne suppose qu’un très bas pourcentage de l’ensemble d’ouvrages répertoriés. À une époque où, dans le panorama scientifique et culturel, les figures phares sont des hommes, cette publication rattrape ces voix, ces sensibilités féminines oubliées, qui, de leur temps, se sont exprimées à travers la nouvelle. Bien que leur dévouement pour ce genre n’ait pas été le même et qu’elles aient été étiquetées par l’Histoire de la Littérature comme romancières, poétesses, dramaturges, journalistes ou tout simplement comme femmes de lettres, la réalité est que, de manière variable, beaucoup d’entre elles ont pratiqué le récit court.
【担当部分】 Kyoko Murata « Stratégie de l’écriture féminine chez Delphine de Girardin : Courrier de Paris » (pp.113-124)
Delphine de Girardin publie en 1836 La Canne de Balzac pour rendre hommage au génie de Balzac. Mais ce dernier, considérant cette nouvelle comme « des mièvreries », lui recommande de franchir « cette désolante distance […] entre les deux sexes ». Cependant loin d’adapter une écriture virile pour faire « un grand, un beau livre », Delphine tiendra désormais à son écriture féminine dans le feuilleton intitulé « Courrier de Paris », situé au « rez-de-chaussée » de La Presse.
Dans cette étude, nous examinons à quelles stratégies médiatiques a recours Delphine de Girardin pour renverser la hiérarchie entre le Premier-Paris (la sphère des hommes), et le Feuilleton (celle des femmes). D’abord, nous comparons le « Courrier de Paris » avec les « Lettres sur Paris » de Balzac, qui servent de modèle du Courrier. Ensuite, nous analysons quelle fonction remplissent la structure mosaïque et le pseudonyme du vicomte Charles de Launay dans le « Courrier de Paris ».
【本書に関する書評】
Cédille. Revista de Estudios Franceses, Vol 10 (2014), pp.421-424 (Marta Ciné)
 【目次】
【目次】 目次
目次