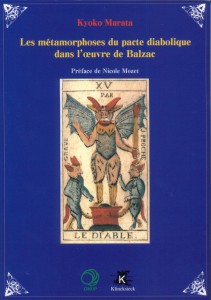著書(単著)
総頁数352頁+別丁カラー図版16頁(出版社サイト:http://www.suiseisha.net/blog/?p=18887)
【概略】作家たちは服装の記号を駆使していかに作品を描いたのか?
前著『イメージで読み解くフランス文学』では、19世紀フランス文学を作品と密接に関連する絵画・彫像と結びつけながら、ジェンダーの視点で考察した。とりわけゾラの『ナナ』や『獲物の分け前』では、女主人公の着る服装は社会的記号となっていた。本書は、その続編として、絵画など美術作品とも連関させながら、モードの観点から文学作品を読み解く試みとなっている。
19世紀は、モード史の観点から見て、服装に大きな変化をもたらした時代であった。フランス革命前のアンシャン・レジーム下では、服装はその形状・質・色が身分別に法律で定められ、とりわけシルクやレース、貴金属など贅沢な装飾品は特権階級のみに許されていた。革命後は「服装の自由」が政令によって明文化され、理論的には誰でも自由に服装を選べるようになった。したがって、服装にこだわりを持つダンディたちを顧客とする高級仕立屋が現れ、女性服に関しても19世紀後半にはオートクチュールの祖、ウォルトが登場する。衣料品店の形態に関しても、従来の薄暗い店舗から明るく大きなショーウィンドーを持ち、色とりどりの布地が美しく並べられた「マガザン・ド・ヌヴォテ」が出現し、さらに第二帝政期にはデパートが誕生する。こうした変化を忠実に反映したのが、同時代の文学先品である。したがって、本書では、19世紀フランス文学を服装やモードを通して、社会的・歴史的・文化的観点およびジェンダーの視点から読み解いた。
第一章では、フランス革命末期の反革命運動を扱ったバルザックの『ふくろう党』を取り上げ、服装と革命の関わりを明らかにしている。第二章では、ジョルジュ・サンドの『アンディヤナ』において、女主人公の服装や変装に焦点を当て、女性作家の視点に立った服装描写の分析を行った。第三章では、バルザックの『幻滅』において、地方とパリの風俗の違いを、服装を通して検証すると同時に、バルザックのダンディズムについて考察した。第四章では、バルザックの『骨董室』と『カディニャン公妃の秘密』に登場する「モードの女王」が、服装の記号を駆使し、どのような女性を演じたのかを検証した。第五章では、エドモン・ド・ゴンクールの『シェリ』を取り上げ、第二帝政期の上流社会(オートクチュールの世界)に生きる女主人公の少女時代から19歳の若さで死ぬまでの成長過程を、服装を通して辿った。第六章では、ゾラの『ボヌール・デ・ダム百貨店』において、デパートがいかに女性の欲望を煽り、買い物熱を掻き立ていくか、その基盤となる「女性の搾取」に焦点を当てて分析した。
以上のような考察によって、時代とともに移り変わるモードを19世紀の作家がどのように捉えていたか、多少なりとも把握できたように思う。さらに、第二章では「ズボンを巡る争い」に触れたが、フランスにおいて女性がズボンを穿く権利を正式に獲得するには、長い年月が必要であった。女性にズボンを穿くことを禁じた1800年の警察条例が廃止されたのは、つい最近(2013年)のことである。このように、服装の問題は19世紀に留まらず、現代にも深く関わるテーマで、本書がこうした問題を考えるきっかけとなれば、幸いである。
【本書に関する書評】
cahier34(日本フランス語フランス文学会、高岡尚子氏、2024年9月、pp.21-23)
総頁数288頁(出版社サイト:http://www.suiseisha.net/blog/?p=11219)
【概略】(白黒図版の他にカラー図版も多数掲載)
〈女/男らしさ〉とは何か?
文学作品は、時代を超越した普遍的な価値観を担うと同時に、作品が生み出された社会におけるジェンダー観を色濃く反映している。とりわけ、「近代小説の祖」とみなされるバルザックが登場してからは、なおさらである。文学史においてバルザックは「レアリスムの祖」と目されているように、現実をありのままに描いた彼の作品は、19世紀当時の社会の風習、思想、ジェンダー観を忠実に反映していると考えられる。それはバルザックに留まらず、19世紀の多くの作家に当てはまる。したがって、本書では「近代小説」をジェンダーの視点から分析していきたい。また、芸術小説、芸術家小説を多く生み出したのも、19世紀の作家たちである。ルーヴル美術館の一般開放や、サロン(官展)への一般参加が認められるようになるのは、フランス革命後であり、革命後に経済的覇権を確立したプチブルジョワたちが文化的教養を求めてサロンに殺到するようになる。また、複製画やリトグラフ(石版画)の普及によって、小説の読者である一般大衆にとって、絵画が身近なものとなった。
それゆえ、本書では19世紀フランス文学を、作品と関連のある絵画や彫像などのイメージを媒介にして、ジェンダーの視点で読み解いていく。さらに本書の特徴は、19世紀に覇権を握ったブルジョワ階級の父権的な価値観に基づく「女らしさ」「男らしさ」の範疇から外れる人物に焦点を絞って、作品を分析していることにある。こうした人物がどのような点で「女らしさ」「男らしさ」に欠けるのかを検証することで、当時のジェンダー観をより一層、浮き彫りにすることができよう。
第一章では、スタール夫人の『コリンヌ』を取り上げ、男の領域とされる「公的空間」で華々しく天分を発揮した女性詩人が、いかに悲劇的な末路を遂げるのか、その過程を絵画・彫像などのイメージを通して探っていく。第二章では、男を破滅させる「宿命の女」像を、「宿命の女」を描いた絵画を参照しながら、19世紀前半のバルザックの作品において検証する。第三章では、ゾラの『ナナ』を取り上げ、19世紀後半の第二帝政期における危険な娼婦像を、印象派のマネの絵画などと関連づけて分析する。第四章では、同じくゾラの『獲物の分け前』を取り上げ、娼婦のナナと対極をなす社交界の女王、ルネの身体がいかに男たちに搾取されていくのか、当時のモード、ファッション・プレートや絵画を通じて見ていく。第五章では、第四章までとは逆に、「男らしさ」の範疇に当てはまらない、両性具有的な男性を取り上げる。そして、彼らがどのように描かれ、どのように「男らしさの危機」と関連しているのか、ロマン主義文学から自然主義文学にかけて探っていく。
こうした分析作業を通じて、19世紀フランスに限らず、現代の日本にも通じる「女らしさ」「男らしさ」の観念への問題提起を行っていきたい。また、絵画・彫像などイメージを介することで、文学作品の読解に新たな視野が広がることを期待している。
【本書に関する紹介記事・書評】
「花だより」15号(2019年11月25日:中村啓佑氏、p.5)
『女性空間』37号(日仏女性研究学会、2020年12月:岡部杏子氏、 pp.125-126)
cahier 27(日本フランス語フランス文学会、2021年3月:高岡尚子氏、pp.24-26)
総頁数 217 頁
【概略】
フランス文学と芸術の関わりは深く、画家、音楽家、彫刻家を主人公とする芸術家小説をはじめとして、音楽や美術に関連する作品が多く見出せる。本書は、絵画がフランス・ロマン主義文学の中でどのように扱われているのかを探るものである。例えば「近代小説の祖」と呼ばれるバルザックは、女性を描写する際に、ラファエロの聖母像など絵画を引きあいに出すことがしばしばであった。しかし、人物描写において絵画を参照するようになるのは、実はバルザックの生きた時代、すなわち19世紀前半からに過ぎない。その理由として、①フランス革命後のルーヴル美術館の一般開放、②複製画やリトグラフ(石版画)の普及、③経済的に余裕のできたプチ・ブルジョワが文化的教養を求めたことの3点を挙げることができる。小説の読者である大衆にとって、絵画はより一層身近な存在となったわけだ。その結果、読者に登場人物のイメージを喚起させるために、絵画を比喩として使うことが可能になった。例えば小説の中で、「彼女はモナリザのような神秘的な微笑を口に浮かべていた」と表現するには、一般的な読者がレオナルド・ダ・ヴィンチの絵を知っていることが前提となる。
文学作品で絵画が言及される場合、それがどのようなメタファーとして使われているのか、見定める必要がある。そこには芸術的要素だけではなく社会的要素、とりわけ人物像には「男らしさ」「女らしさ」に関する当時の社会的通念が無意識のうちに投影されている。それゆえ、こうしたジェンダーの観点から、バルザックやテオフィル・ゴーチエ、マルスリーヌ・デボルド=ヴァルモール、ジョルジュ・サンドらロマン主義作家の作品を取り上げ、絵画受容の相違点―とりわけ男性作家と女性作家の視点の違い―を浮き彫りにする。以上のように、本書では文学作品と絵画との相関性を探ることで、文学作品の新たな読解を試みていきたい。
【本書に関する書評・紹介記事】
『ふみのさと便り』21号(2015年3月21日:中村啓佑氏)
『ふらんす』(白水社)(2015年8月号:小倉孝誠氏)
日本フランス語フランス文学会cahier17(2016年3月:坂本千代氏、pp.33-34)
総頁数272頁
【概要】
フランスにおいて、真の職業作家が誕生したのは大革命以降の19世紀になってからである。普通教育の普及や印刷術の発達によって、文学が一般大衆にとって身近なものとなり、作家は筆一本で身を立てることができるようになった。女性作家も同様で、18世紀までは、文学の担い手は貴族または裕福なブルジョワ階級の女性で、生活のためにペンを執ったわけではなかった。それに対して、19世紀の作家ジョルジュ・サンドは約90篇の小説、戯曲、旅行記などを出版して、その印税で大勢の家族を養った。
19世紀のフランス女性作家のうち、サンドとスタール夫人はロマン主義およびフェミニズム運動の先駆者として、日本でもよく知られている。しかし、この他にも数は少ないとはいえ、様々な階級の独創的な女性職業作家が誕生した。日本ではあまり知られていない、こうした女性作家たちを発掘し、彼女たちがどのような生き方をして、どのような作品を生み出したのか、その作品に反映されている女性の視点とはどのようなものかを探るのが、本書の狙いである。
本書ではまず、近代小説の祖バルザックの作品を軸に、男性中心であった19世紀文壇の実態をジェンダーの視点から浮き彫りにする。次に、国王ルイ・フィリップの養育掛を務めたジャンリス夫人、女性ジャーナリストの草分けであるデルフィーヌ・ド・ジラルダン、そして労働者階級出身で労働者階級の解放に身を捧げたフロラ・トリスタンに光を当て、「女がペンを執る時」とはどのような時なのかを明らかにする。出自も思想も様々な女性職業作家たちを扱う本書は、「女・文学・社会・労働」といった現在にも通用する普遍的なテーマを考える上でも、一つの足がかりとなろう。
【本書に関する書評】
『読書人』(2011年12月23日:高木勇夫氏)
日本フランス語フランス文学会書評:cahier No.9, 2012年3月pp.16-18(高岡尚子氏)

総頁数350頁
【概要】
19世紀フランス・ロマン主義文学において、クルチザンヌ(娼婦)の存在は重要な位置を占めている。とりわけ、アベ・プレヴォーの『マノン・レスコー』やデュマ・フィスの『椿姫』の主人公の名は、誰でも一度は耳にしたことがあるに違いない。こうした作品は、真実の愛に目覚めた娼婦が悔い改めて苦難の道を歩み、罪を贖って死ぬ恋愛物語として、読者に共感と同情の涙を誘ってきた。しかし、私たちはそれが男性の視点で描かれていることに気づかないことが多い。私たちは実は、男の主人公(または男性作家)の眼を通して、男の抱く理想の女性像をこれらの作品に見出し、そのイメージを共有していたのだ。
では、発想を転換して、女の視点、ジェンダーの観点から見ればどうなるだろうか。本書は、男性の視点に立った従来の解釈とは全く異なる立場から、文学作品を読み直そうとするものである。取り上げる作品は『マノン・レスコー』、『椿姫』の他にジョルジュ・サンドの『イジドラ』、バルザックの『マラナの女たち』『娼婦盛衰記』『従妹ベット』、ウージェーヌ・シューの『パリの秘密』、ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』など多岐に渡っている。
クルチザンヌが文学に登場する19世紀は、産業革命やブルジョワジーの台頭により、資本主義が確立した時代である。それは、すべてがお金に換算され、「女の肉体」も「商品」として男の手から手へと流通する時代の幕開けであった。このことはまさに、市場主義が推し進められた現代社会のルーツを成している。私たちの社会の原点である近代社会を描いたフランス・ロマン主義文学の世界に立ち戻って娼婦像を考察することは、現代の女性像の原点にさかのぼることでもあろう。現在、取りざたされることの多いジェンダーに基づく価値観(「男らしさ」「女らしさ」の概念)を考える上でも、本書は一つの足がかりとなろう。ロマン主義的クルチザンヌの分析を通じて、現代につながる諸問題を浮き彫りにするのが本書の狙いでもある。なお、本書は3.にあげた科学研究費補助金基盤研究「フランス・ロマン主義文学におけるクルチザンヌ像」の研究成果報告書に加筆・修正を施したものである。
【本書に関する書評】
日本フランス語フランス文学会書評 cahier01 2018年3月(松本伊嵯子氏)pp.12-14
Osaka Municipal Universities Press/Klincksieck (Paris), 2003(総頁数328頁)
【概要】
本書は「近代小説の祖」と謳われるバルザックの作品に現れる「悪魔との契約」のテーマに注目し、その変遷を辿ったものである。19世紀のヨーロッパにおいて、ゲーテの『ファウスト』をはじめ、多くの文学作品(幻想文学)がこのテーマを扱ってきた。超自然的な存在が否定された合理主義の時代になぜこのテーマが流行したのであろうか? その答えとしては、逆説ながら、理性の時代であるが故に「悪魔」という表象が文学に現れたと言える。すなわち、それまで信じられてきた「奇跡」が「迷信」として退けられるようになったからこそ、不合理な出来事が生じた時に人々が受ける衝撃は大きく、不安が増す。こうした未知なものへの不安をいち早く捉えて言葉で表そうとしたのが文学作品であった。
本書第一部では、「幻想文学」のジャンルに入るバルザックの作品(『百歳の人』『あら皮』『和解したメルモス』)を取り上げている。そこではもはや従来の「悪魔との契約」(現世の富や知識欲の充足と引き換えに来世の魂を悪魔に売る)は成り立たず、現世の快楽と引き換えるのは、この世の命(寿命)である。その結果、短いが激しい情熱的な生を生きるか、機械的な生活をして長生きするかの二者択一を迫られ、「悪魔との契約」は近代の欲望哲学の表徴となる。また、『和解したメルモス』では、悪魔の超自然的な力も株式取引所で需要・供給の法則に従って売られ、その力を失っていく。「サタンの最後」と言えるが、その代わりに別な形で悪魔的な存在が描かれることになる。
第二部では、現実的な空間における「悪魔」、「悪魔との契約」が意味するものを明らかにしていく。『ゴリオ爺さん』に登場するヴォートランをはじめとする「悪魔的な人物」は全て、社会から疎外された存在で、社会の周縁から社会征服を目指す時、体制側から見れば「悪魔的」に映る。商業小説『セザール・ビロトー』では、古い伝統的な価値観を擁する主人公のビロトーから見れば、台頭し始めた資本主義的価値観の持ち主はすべて「悪魔的」である。『結婚契約』や『従妹ベット』では、家父長的な社会に異議申し立てを行う女性が「悪魔的」と捉えられている。このように、古い価値観から新しい価値観への移行期にあって、既成の秩序、思想体系を脅かす存在が「悪魔」とみなされている。
こうした「悪魔」、「悪魔との契約」のテーマはバルザックの時代だけではなく、政治的・社会的・経済的な変動期にある現代にもあてはまる問題を提起していると言えよう。
【本書に関する書評】
Romantisme, No.125, 2005 (pdfファイル)
Nineteenth Century French Studies, vol. 33, 2005 (pdfファイル)
L’Année balzacienne 2005 (pdfファイル)
Revue d’histoire littéraire de la France, avril-Juin 2005 (pdfファイル)
 【目次】
【目次】 目次
目次