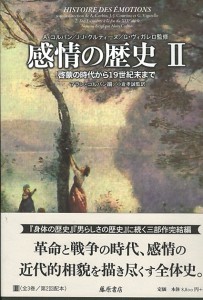 本書は、アラン・コルバン、ジャン=ジャック・クルティーヌ、ジョルジュ・ヴィガレロ監修による『感情の歴史』(Histoire des émotions) 全3巻の、第Ⅰ巻『古代から啓蒙の時代まで』に続く第Ⅱ巻『啓蒙の時代から19世紀末まで』〔アラン・コルバン編、小倉孝誠監訳、総頁数669p.〕の翻訳書である(第Ⅲ巻は『19世紀末から現代まで』)。さらに、『感情の歴史』は、既に翻訳書が出ている『身体の歴史』『男らしさの歴史』に続く三部作の完結編ともなっている。本書は8人で翻訳を担当し、村田もその一員である。
本書は、アラン・コルバン、ジャン=ジャック・クルティーヌ、ジョルジュ・ヴィガレロ監修による『感情の歴史』(Histoire des émotions) 全3巻の、第Ⅰ巻『古代から啓蒙の時代まで』に続く第Ⅱ巻『啓蒙の時代から19世紀末まで』〔アラン・コルバン編、小倉孝誠監訳、総頁数669p.〕の翻訳書である(第Ⅲ巻は『19世紀末から現代まで』)。さらに、『感情の歴史』は、既に翻訳書が出ている『身体の歴史』『男らしさの歴史』に続く三部作の完結編ともなっている。本書は8人で翻訳を担当し、村田もその一員である。
「感情」は時代や文化、個人によってその現れ方が違う。本書の「総序」の一部を引用してみよう。「恐怖、恥辱、怒り、喜びはおそらくいつの時代にも観察されるし、一つの時代から別の時代になっても理解され、「把握される」ように思われるが、じつは個人によって、文化によって、感受性によって異なるのだ。これらの感情には独自の状態と変遷があり、変化し、個別化し、一般的に広く存在するとはいえ細分化された可能性を示す。」こうした「感情の歴史」を時系列的に様々な観点から探ったのが本書で、とりわけ19世紀は「感情の歴史」においてきわめて豊かな時代であった。すなわち、「繊細な魂の覚醒とそれに由来するものが、人々の感動のしかたや特異な感情のゆるやかな刷新によってきわめて特殊な時代を描きだす。こうして個人の内面であれ、自然と他者と社会を感じる新たな方法が生まれる」(「序文」より)時代であった。
本書は16章に分かれ、各専門分野の研究者による論文集となっている。その特徴は次のようなものだ。「内面性、私生活、気候、風景、革命、政治運動、戦争、死刑、宗教、芸術などは、いずれも文化史、社会史、政治史、制度史、宗教史、文化史、美術史の分野で研究され、見事な成果をあげてきた。それを個人と共同体の感情という視座から分析した本書の各章は、人間の歴史の新たな側面を浮き彫りにしてくれたのである。感情は個人レベルにとどまるものではなく、集団的な次元を有する。その境界線はしばしば微妙だが、感情の集団的次元に絶えず配慮しているのが本書の価値の一つであろう」(「監訳者解説」より)。さらにその分析の手段として自伝や回想録、手記、日記、書簡など「個人の内面性とプライバシーを伝える言説」(同上)を積極的に活用し、警察や司法関連資料など公的資料には見いだせない文学的要素と深く関わっていることも本書の特徴である。
【翻訳担当部分】
・アニェス・ヴァルシュ「第9章:感じやすい魂から感情の科学的出現へ――私的領域における感情の濃密化」(pp.309-340)
・ギヨーム・キュシェ「第14章:宗教的感情の刷新」(pp.471-511)